
佐久総合病院ニュースアーカイブス  |


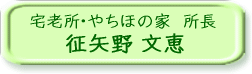
やちほの家のカーテンは、8時10分頃にようやく開く。宅老所が始まって半年、まだ昼間だけの通所サービスなので、職員の出勤がないと開かない。夜だけでも、人が居ない家の朝の冷え込みは、身体にしみる。6月に入ってようやく、炬燵だけで過ごせるようになった。カーテンを開けると、すでにお日様は高いところで照っている。1年で最も日が長い季節である。いつものように留守番電話が点滅している。留守電は無言。でも誰だかすぐわかる。
87歳のおばあちゃんは軽い認知症がある。季節感や日時の見当識障害がある。思い立ったら待てないのである。早速、受話器を取る「おはよう。調子はどうだい。電話ありがとうね」「何だい。居ただかい。どこへ行っていただい」「ごめんね。今帰ってきたから、これから迎えに行くよ。待っててね」お日様が高くなると、おばあちゃんの身体時計が早まるのである。最近は、こてっ早にやちほの家へ向かって歩いているおばあちゃんの姿は収まっている。
おばあちゃんは、やちほの家に決まってエプロンと、ズボンの後ろに日本手拭いを挟んでくる。やちほの家のどの場所でも、この姿はいやに馴染んでいる。来たいときに来て、気が進まないときは休む。この自由さが心身の安定につながっている。かつておばあちゃんは、週1回のデイサービスの日がわからなくて、違う曜日に歩いてきてしまったり、近所に聞きに回ったりと不穏の日々があったが、それが嘘のようだ。利用者本位のサービスにしていくには、計画ありきのサービスでは通らないことも多いのである。
94歳のばあちゃんは、息子と2人で暮らしている。白内障が進んだ眼は幾分白く濁っている。背骨は、相当重い物を背負い込んで来たのだろうかSの字に曲がって、若い頃に比べ、1回りも2回りもからだが小さくなっている。「おはよう。迎えに来たよ。さぁ行かずい」「何だい。どこへ行くだい」と、炬燵に潜り込んで視点の定まらない目で私を見ている。一緒に炬燵へ入り込んで、ばあちゃんのその気になるのをしばらく待つ。前回宅老所へ行った日も、場所もばあちゃんの記憶に残されていない。ばあちゃんは、1日30本の煙草をふかし、ビールも飲む。家に居ると口寂しいからだという。「こんなに長生きして困るだに。みんなに世話になって看てもらってありがてぇこった。良い時代になったもんだ。わざわざ迎えに来てくれただかい」いつもの言葉が始まった。ばあちゃんは、細々しい腕で自分の身体を支えるように起きあがると、ようやく意識の中に私が入り込んだようだ。お風呂を洗っていたのか、奥から息子が顔を出した。「さっきまで行くといっていたのに全くこれだい」ちょっと高台にあるばあちゃんの家は、コンクリートの階段を十段降りていく。ちょっとの風でもよろめいてしまうような、おぼつかない足取りだが、何故か車に乗り込む姿はすばしっこい。ばあちゃんのからだが助手席のシートに吸い込まれていく。窓越しの風景を、背伸びしながら白く濁った眼で見ている。「ここも随分開けたもんだ。えらい変わったわい。俺も一元に呼ばれただかい」ばあちゃんの補聴器がピーピー鳴っている。宅老所でのみんなとの共食は一元に呼ばれたと思っている。
|
|