


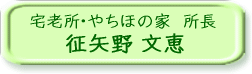
先月娘さんから電話が入った。聞き覚えのある落ち着いた声に幾分弾みがある。あれから5年余。年数を重ねた分さぞかし娘さんの白髪も増えただろうにと、電話の向こうの声を一つひとつ拾いながら、昔の記憶を辿っていく。「10日前に母を送りました。母も最後の方は皆さんに感謝する心持ちが持て、穏やかに逝ってくれて良かったです」。「感謝して・穏やかに」という響きに、娘さんの安堵した気持ちがあふれて、ふぁっと私の中に温かさが伝わってくる。思いも寄らない電話に感謝しつつ、これもおばあさんが長い間に残していった「つながり」という「糸」なんだと納得する。
大正の始めに生まれたおばあさんは、関わってきたお年寄りの中で五本指に入るほどの男勝りの豪傑な人だった。まだまだ女盛りという年に未亡人となり、ひとりで旅館業と子育てを切り盛りしてきたという。
 おばあさんとの出会いは12年前。持病の脊椎疾患の悪化による入院治療にめどが付き、在宅生活に向けて退院調整がされた。「この状態であれば、5年の間に確実に寝たきりになります。ひとりでの生活はもう困難です」という主治医の宣告をきっかけに、遠方から子どもたちが集まって、家族会議が何度も開かれた。結果的には、安定と不安定を繰り返しながら、徐々に動作は低下していったものの、在宅や施設サービスを使いながら7年余独居で過ごし、寝たきりになったのは、特養入所後の脳梗塞発症が原因になったようだ。 おばあさんとの出会いは12年前。持病の脊椎疾患の悪化による入院治療にめどが付き、在宅生活に向けて退院調整がされた。「この状態であれば、5年の間に確実に寝たきりになります。ひとりでの生活はもう困難です」という主治医の宣告をきっかけに、遠方から子どもたちが集まって、家族会議が何度も開かれた。結果的には、安定と不安定を繰り返しながら、徐々に動作は低下していったものの、在宅や施設サービスを使いながら7年余独居で過ごし、寝たきりになったのは、特養入所後の脳梗塞発症が原因になったようだ。
元気な頃、おばあさんはヘルパーに、庭だけでなく墓場の草刈りも頼んだ。一緒にお茶を飲み饅頭や蕗菓子を作らせてはお仕え物にした。時間の制限なくサービスは提供されていた。今までのサービスは法律で提供できないこと、生活に必要なサービスであれば派遣できること、しかもサービスは有料であることについて、何としても納得してくれなかった。「身の回りのことぐらい自分でできる。人様に世話になるほど落ちぶれちゃいないわい」。
長年の自己道尿ができなくなり、排泄や清潔援助で訪問看護も導入された。ケアが終わると、訪問看護婦の顔を見てちゃっかり使っていた。「米を二合洗っておしかけしておくれ。ただ歩かないで、足下にある草を抜きながら歩いて行くもんだ。雨戸を閉めて行っとくれ」。
おばあさんは切れ長の目で人をよく見る。でも見ている目は、大概自分にとって都合がいいか、使えるかという目で見極めている。長年の商売気質が染みついている。むしろおばあさんは正直者なのである。弱音や感謝の気持ちを出すことが苦手なのである。頼ることや任せることが苦手で、自分の好きなように生きることを主張したからこそ、娘さん夫婦もおばあさんを尊重し、最後まで自分の身の振り方について自己決定をさせてきた。しかもおばあさんの決定に娘さん夫婦はいつも寄り添ってきた。そしておばあさんも、葛藤はあっただろうが自己責任・自己決定を放棄しなかったように私には思われる。
「介護」「見送る」ことについて、おばあさんを中心にした頻回の「家族会議」。おばあさんを中心とした「おばあちゃん基金」。最後何処で過ごしたいか、何処で死にたいかをどう考えていくのか、人ごとでない。
|
|