


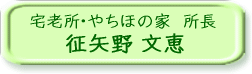
おばちゃんの介護はまだ終止符を打つことはできない。あれは13年前、おばちゃんの義理の「姉さん」は、すこぶる足が丈夫だった。毎日リュックサックを背負って、もんぺを履いて、急坂をゴム足の音をキュッキュッとたてて、半里を勢いよく下ってくる。真夏の炎天下であっても、大雪の日であっても、休むことなく下ってくる。元来化粧っ気のない「姉さん」の顔は、時には燦々と照る太陽の日差しに、時には横殴りに頬を打つ寒風によって、元来の赤ら顔が腫れて、細い目を押し上げている。そんな時は「姉さん」の持病の高血圧が、見るからに悪さをしているように見える。しかし「姉さん」は、血圧の180や200の声を聞いても平気のへっちゃんだ。「ちったぁ高くても、昔から世話になった大先生の薬を飲んでいるから心配ねぇわい」というものの、殆ど診察にも行っていない。
 数年前から始まった「姉さん」の物忘れがいよいよ進み、作業ができなくなった。しかし「姉さん」は、相変わらずリュックサックを背負って歩いている。時々道に迷って保護されたり探し回ったりと、「姉さん」への関わりや介護が、おばちゃんに求められ始めていた。しかし、若い頃から、住み込みで働きに出て、その間結婚もせず自由気ままに生活してきた「姉さん」、同居後も農業や家の手伝いは一切せず、年金で気ままさを通してきた「姉さん」の姿が、専業で余裕なく切り盛りしてきたおばちゃんの心に、戸惑いやブレーキを掛けていく。 数年前から始まった「姉さん」の物忘れがいよいよ進み、作業ができなくなった。しかし「姉さん」は、相変わらずリュックサックを背負って歩いている。時々道に迷って保護されたり探し回ったりと、「姉さん」への関わりや介護が、おばちゃんに求められ始めていた。しかし、若い頃から、住み込みで働きに出て、その間結婚もせず自由気ままに生活してきた「姉さん」、同居後も農業や家の手伝いは一切せず、年金で気ままさを通してきた「姉さん」の姿が、専業で余裕なく切り盛りしてきたおばちゃんの心に、戸惑いやブレーキを掛けていく。
おばちゃんは小柄ですっかり腰が曲がっている。夫は横座で一杯飲み、おばちゃんは忙しく動きながらも、頃合いを見て夫の茶碗に一升瓶を注ぐ。おばちゃんひとりがいつも動いている家だった。
そんな矢先「姉さん」が脳梗塞で倒れた。「姉さん」は重度の左麻痺と言語障害となった。高齢でかつ認知症の影響もあり、リハビリが思うように進まず、気力の低下も合わさって、座位保持以外全介助の状態で自宅へ帰ってきた。おばちゃんは、小柄な体を効率良く使うために、ベッドの上から「姉さん」にまたがりオムツを替え、食事を養い、汚染された山ほどの洗濯物を切り盛りし、やっぱりひとりで動いていた。
何時だっておばちゃんは嘆く。「どんなに病気であっても、せめて『ありがとう』の一言ぐらいは言えないものかい?」「ご飯の時ぐらいせめて『美味しい』の一言ぐらいは言えないものかい?」「言えないんだったら、せめて笑うとか何とかできないものかい?」
「姉さん」を送って1年、5年もの長い介護に安堵し、長年煩ってきた自分の腰や膝の治療にも目を向けられるようになってきた矢先、夫が倒れた。動きが悪くなって3日目にようやく、おばちゃんに説得されての入院だった。脳梗塞による重度の片麻痺。おばちゃんの介護は、やっと見送ったはずの「姉さん」のあの介護の始まった日に、時計を戻されたように感じた。しかし、湾曲した腰も膝も、おばちゃんをより一層小さくさせていた。
|
|